Gradio 6のgr.HTMLで、Pythonファイル1つから完全なWebアプリが作れるようになった
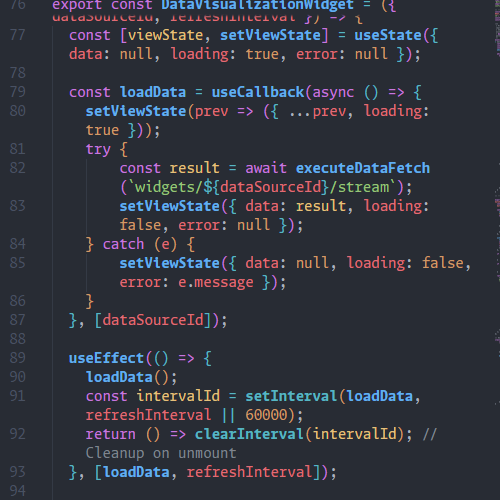
Hugging FaceがGradio 6で追加したgr.HTMLがなかなか強力だった。HTML、CSS、JavaScriptをすべてPythonファイルの中に書いて、ビルドステップなしでインタラクティブなWebアプリを作れる。LLMにコードを生成させて一発でアプリを立ち上げる「ワンショット開発」との相性が抜群に良い。
gr.HTMLの基本的な仕組み
gr.HTMLはGradioのコンポーネントで、以下の4つの要素をPythonコード内に記述する。
html_template— HTMLテンプレート。${value.xxx}で状態を注入できるcss_template— スコープ付きCSS。他のコンポーネントに影響しないjs_on_load— JavaScriptのイベントハンドリングとDOM操作value— PythonとJavaScript間で自動同期される状態
gr.HTML(
value={"count": 0},
html_template="<button>Clicked ${value.count} times</button>",
css_template="button { background: #667eea; color: white; }",
js_on_load="""
element.querySelector('button').onclick = () => {
props.value = { count: props.value.count + 1 };
trigger('change');
};
"""
)props.valueへの代入でJavaScript側の状態を更新し、trigger('change')でPython側に同期する。双方向データバインディングが自動で動く仕組みだ。
再利用可能なコンポーネントの作成
gr.HTMLをサブクラス化することで、gr.Imageやgr.Sliderと同じように扱えるカスタムコンポーネントを作れる。
class Heatmap(gr.HTML):
def __init__(self, value=None, theme="green", **kwargs):
super().__init__(
value=value,
theme=theme,
html_template=TEMPLATE,
css_template=STYLES,
js_on_load=SCRIPT,
**kwargs
)サブクラス化したコンポーネントはGradioのイベントハンドラ(.change()、.click()など)がそのまま使える。MLパイプラインに独自のビジュアライゼーションを組み込むときに便利だ。
実用的なユースケース
Hugging Faceのブログでは以下のような実例が紹介されている。
プロダクティビティ系 — ポモドーロタイマー(ピクセルアートのアニメーション付き)、GitHubコントリビューションヒートマップ、カンバンボード(ドラッグ&ドロップ、インライン編集、リアルタイム検索対応)
3D・メディア系 — Three.jsを使ったカメラコントロールビューポート、リアルタイム音声書き起こし(WPMカウンター付き)
ML特化 — 物体検出のバウンディングボックスとセグメンテーションマスクの表示、ポーズ推定のスケルトン描画
どれもPythonファイル1つで完結する。Reactやビルド設定は不要。
LLMとの相性
gr.HTMLの設計が一番活きるのは、LLMにコードを生成させるケースだろう。従来のWebアプリ開発では、HTML・CSS・JavaScript・Python(またはバックエンド言語)を別々のファイルに分け、ビルド設定やデプロイパイプラインを整える必要があった。
gr.HTMLならすべてが1つのPythonファイルに収まる。LLMに「こういうUIのアプリを作って」と指示すると、ファイル1つで動くコードが返ってくる。gradio app.pyで即座に起動でき、リロードモードを使えば秒単位でイテレーションが回る。Hugging Face Spacesへのデプロイもgradio deploy一発だ。
Gradioは元々MLモデルのデモ用UIフレームワークとして使われてきたが、gr.HTMLの追加で汎用のWebアプリフレームワークとしての性格が強まった。ビルドレスで動く点とLLM生成コードとの親和性の高さは、AI時代のプロトタイピングツールとして理にかなっている。
元記事: Hugging Face Blog